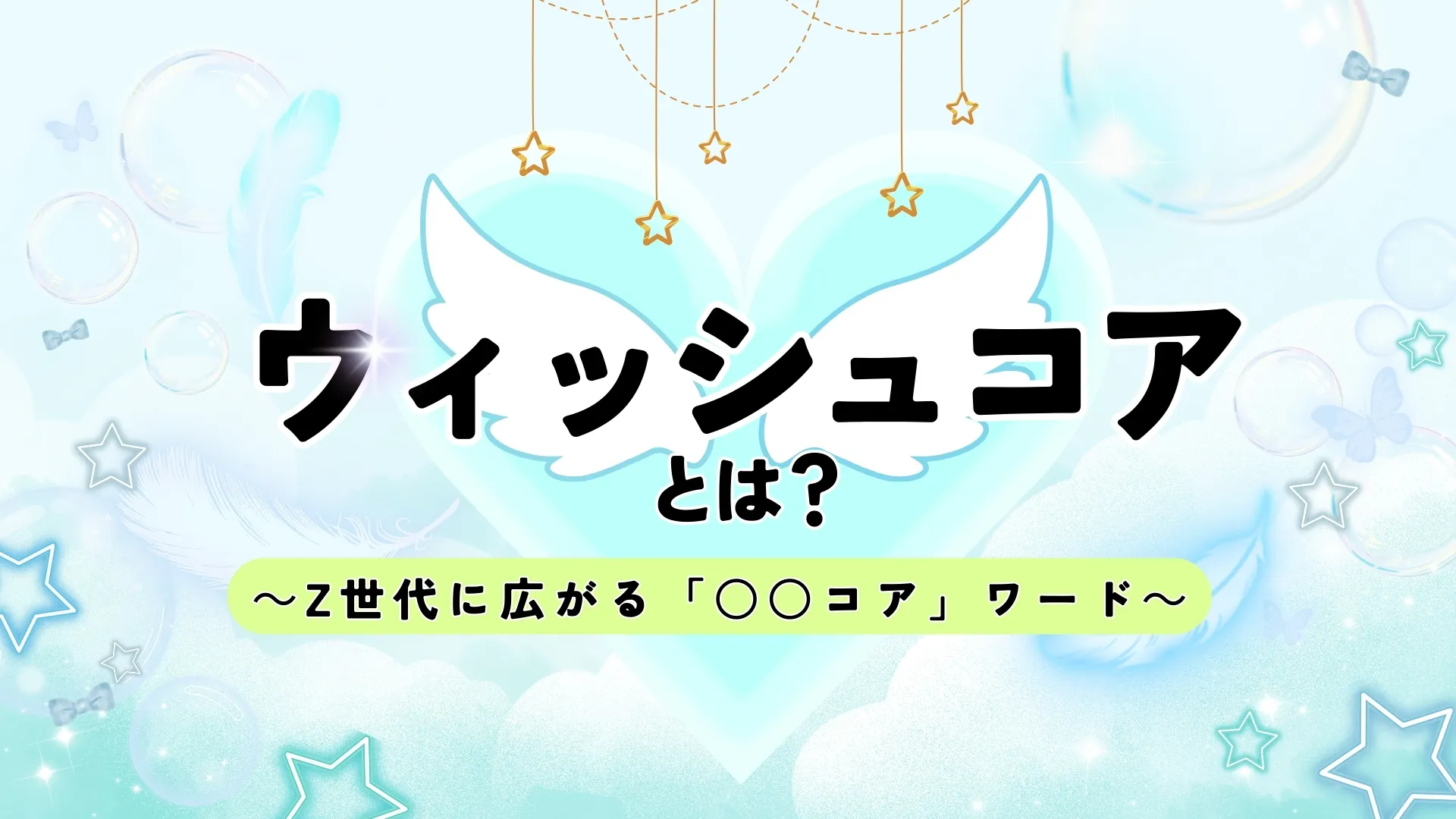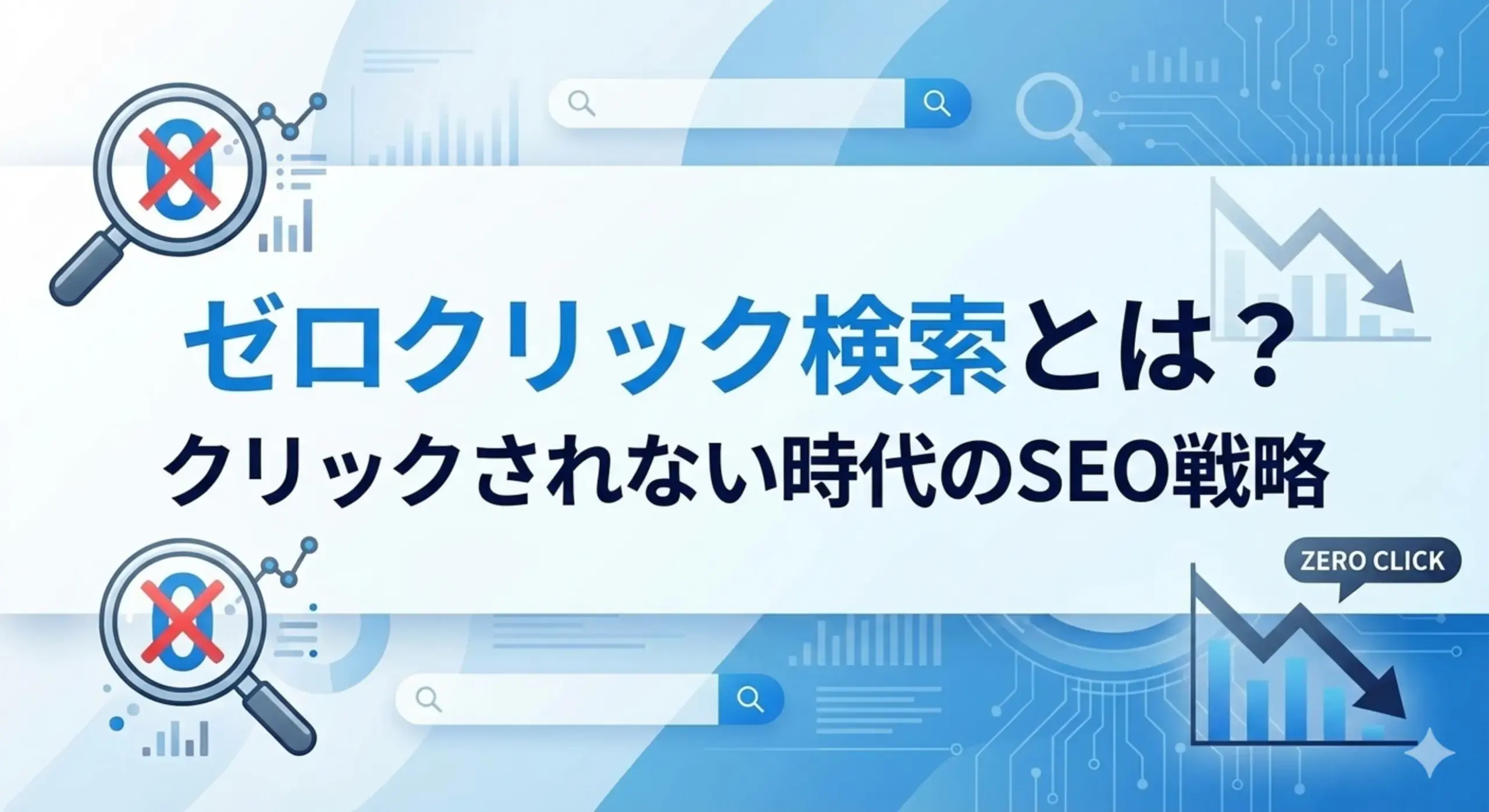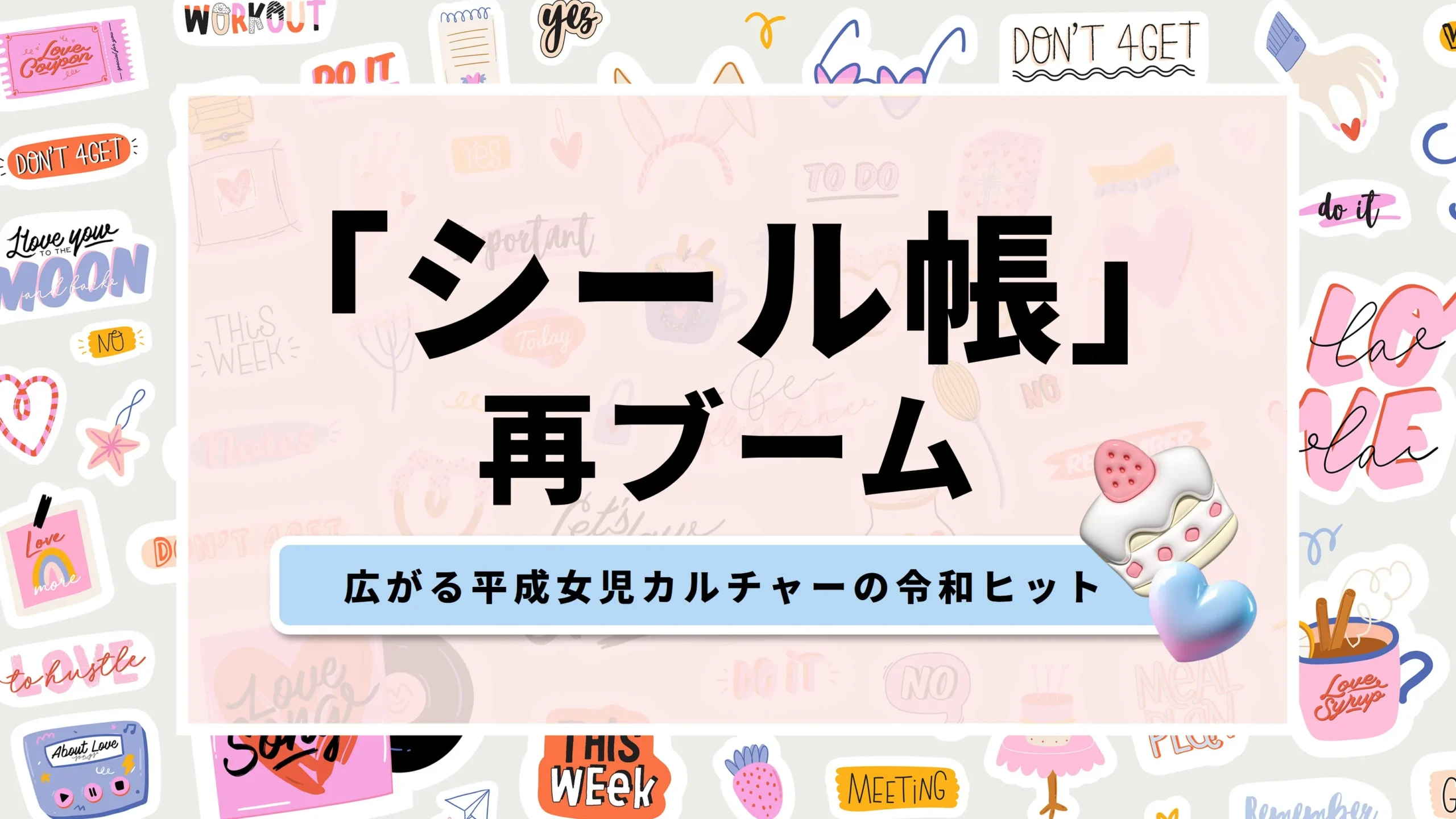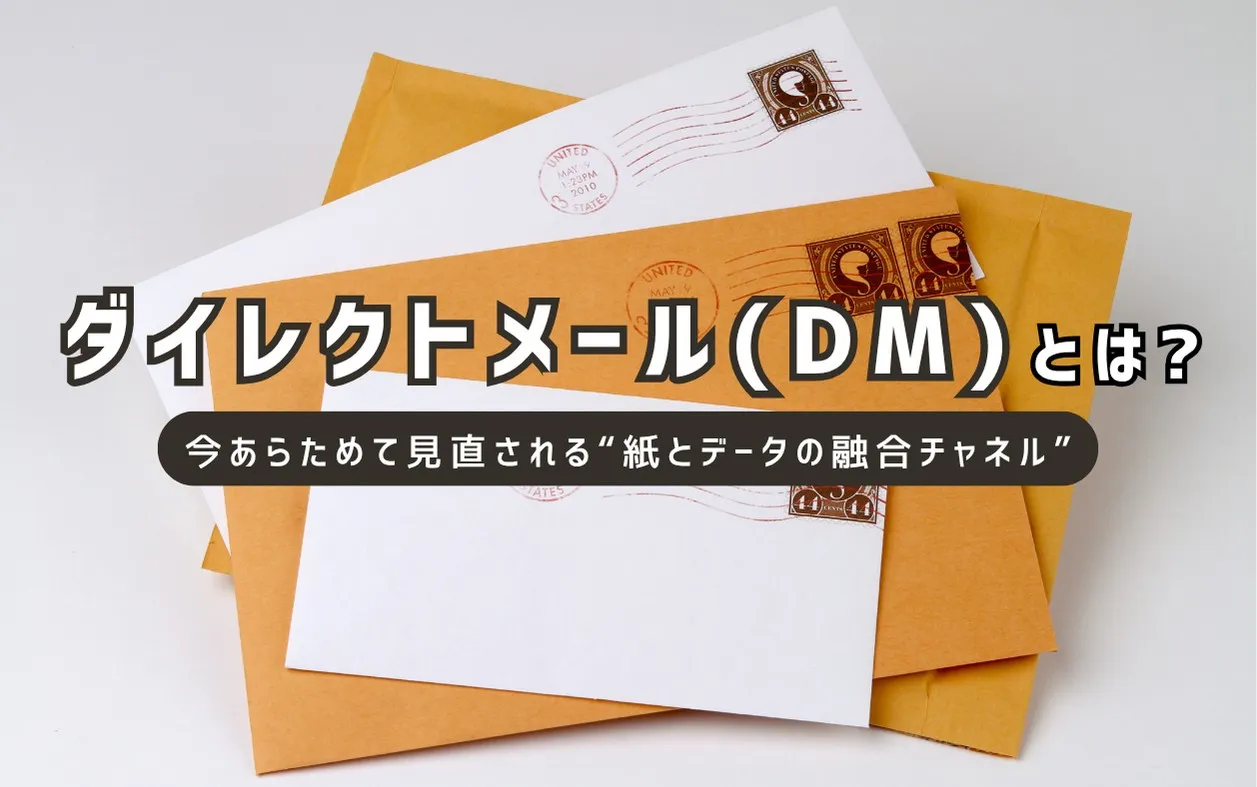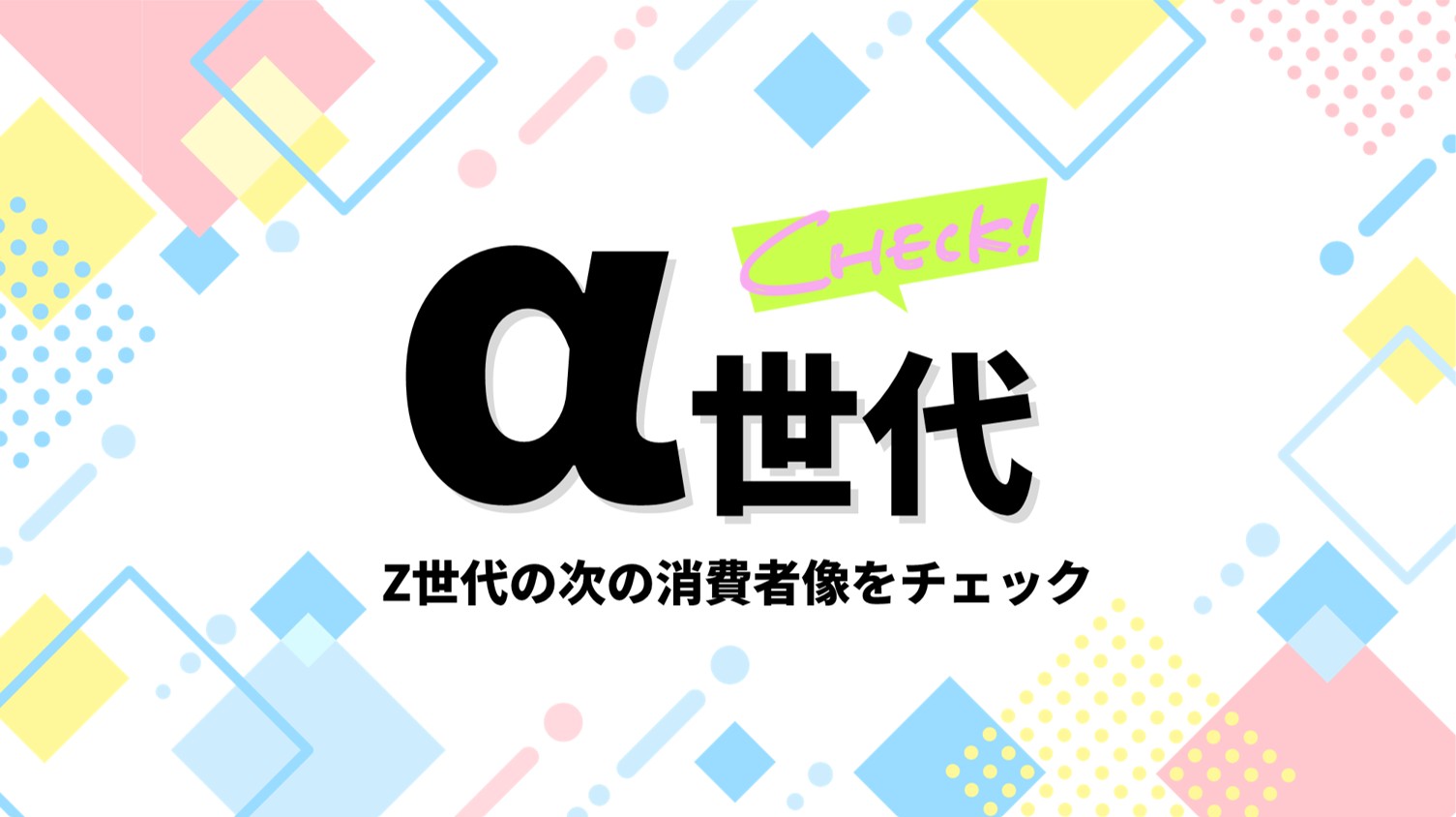ファンダムマーケティングとは?事例に学ぶ熱量の活かし方
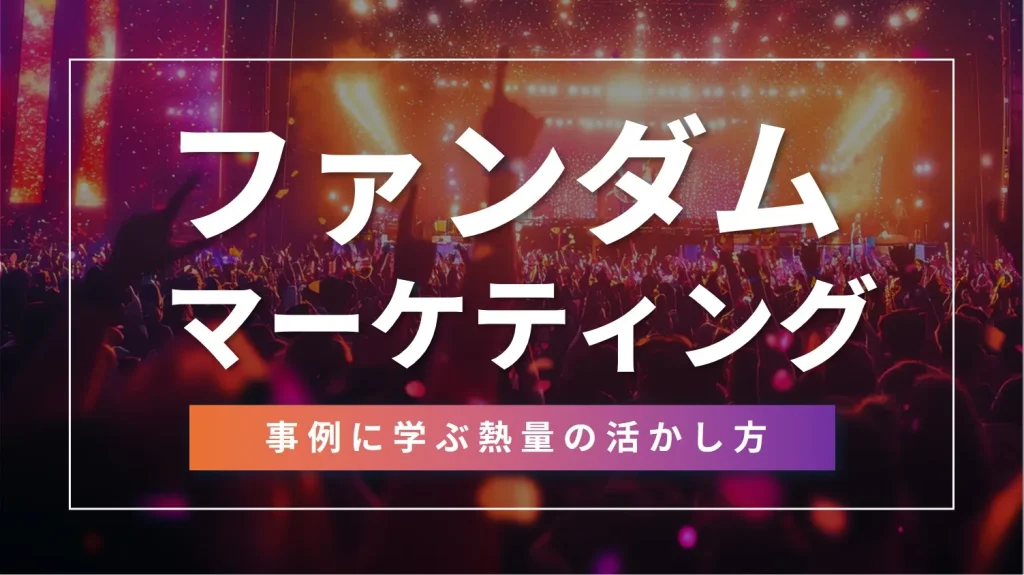
ブランドや商品の魅力をどう伝えれば、人々に長く支持されるのか。
この問いに、多くの企業が頭を悩ませています。
SNSや広告での発信が当たり前になった今、ただ情報を届けるだけでは人の心は動きません。
そこで注目されているのがファンダムマーケティング。
熱量のあるファンとつながり、ブランドと一緒に盛り上がる仕組みをつくることで、
購買や来店、そして次のプロモーションにつながる“応援の連鎖”が生まれます。
本記事では、ファンダムの基本から事例、そしてプロモーションで活かすためのヒントを紹介します。
▼ファンダムが集まるポップアップストア空間のビーツの事例を多数紹介中!

ファンダムとは?熱量がブランドを動かす理由
「ファンダム」という言葉は、英語の「fan(ファン)」と「dom(領域・世界)」を組み合わせた造語です。
もともとは音楽や映画、アイドルなどの分野で、熱心なファンの集まりを指す言葉として使われてきました。
特に韓国ではこの「ファンダム文化」が成熟しており、K-POPアイドルを応援するファンがSNSで一斉に投稿したり、クラウドファンディングで応援広告を出したりする動きはよく知られています。
日本でも、K-POP人気の広がりとともに「ファンダム」という言葉が一般的に使われるようになってきました。
マーケティングの文脈で捉えると、ファンダム=特定のブランドや商品に強い共感を抱き、能動的に情報発信や購買行動を行うファンの集まりと捉えるとわかりやすいのではないでしょうか。
具体的な行動の例としては・・・
・推しのコラボ商品の全種類を“コンプ買い”する
・SNSで推しに関する体験をシェアし、友人に勧める
・ポップアップや展示会を「聖地巡礼」のように訪れる
・応援広告やクラファンに自ら参加する
たとえば日本では、SNS上で「○○界隈」という言葉もよく使われます。
「コスメ界隈」「カフェ界隈」など、界隈は“共通の関心でつながるゆるやかな集まり”を指し、ファンダムはその中から特に熱量の高いファンが集まった存在です。
言い換えれば、「界隈の中で最もブランドに力を与えるコア層」がファンダムといえます。
だからこそ、ファンダムを味方につけたブランドは、広告以上の拡散力と継続的な支持を得ることができます。
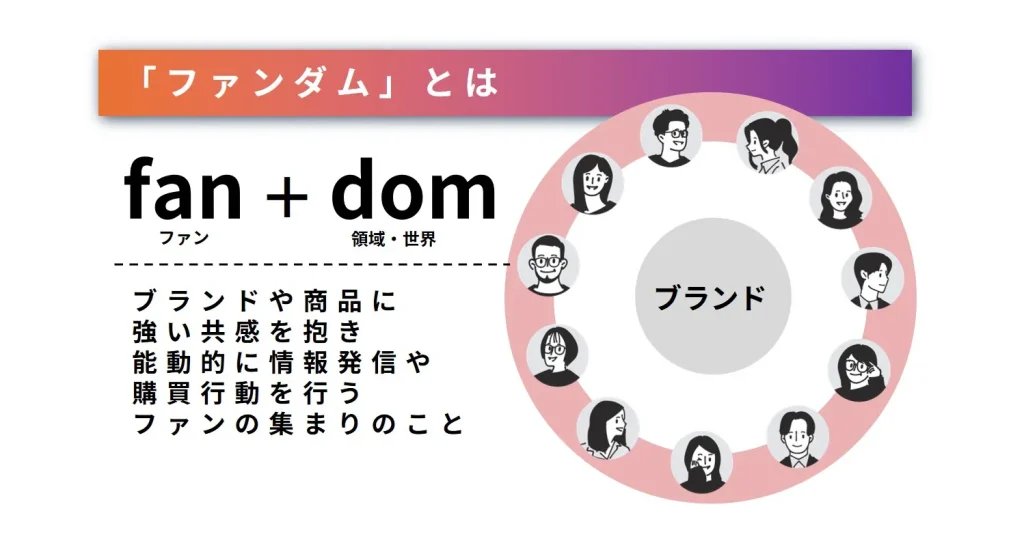
ファンダムマーケティングを成功させる3つの視点
ファンダムは前述の通りもともと音楽やアイドル文化から広がった言葉ですが、いまは企業のマーケティング戦略にも応用されています。
そこで生まれた考え方が「ファンダムマーケティング」です。
ファンダムマーケティングとは、熱量の高いファンをブランドのパートナーとして捉え、その発信力や行動力を活かして認知拡大・購買促進・ロイヤルティ醸成につなげる手法のこと。
単なる消費者として扱うのではなく、一緒にブランドを育てていく存在として関わる点が特徴です。
そのうえで、ファンダムマーケティングを実践する際に欠かせないのが次の3つの視点です。
「響く相手」を見極める
ファンダムマーケティングは、全員に好かれることを目指すのではなく、「自分のためのブランドだ」と感じてもらえる層を絞り込むことから始まります。
広く浅くではなく、深い共感を得ることで、自然に発信や来店につながっていきます。
ファンの文化を読み解く
ファンダムマーケティングを成功させるには、ファン独自の文化やルールを理解することが欠かせません。
ハッシュタグでの活動や、グッズを通じた交流など、ファンが自分たちの文化を大切にしている部分に寄り添うと、ブランドへの信頼は一気に高まります。
「一度の盛り上がり」で終わらせない
ファンダムマーケティングは短期的なバズを狙うものではなく、熱を継続させる仕組みをつくることが本質です。
キャンペーンやイベントの熱量を、コミュニティ運営や次のリアル体験につなげることで、ブランドとの距離はさらに縮まります。

◆◆◆まとめ
ファンダムマーケティングを進めるうえで大切なのは:
①すべての人に届けるのではなく「響く相手」を見極めること
②ファン独自の文化を理解し、自然に寄り添うこと
③一度きりではなく、継続的な関係を育むこと
この3つを意識することで、ファンダムマーケティングは単なるキャンペーンではなく、ブランドを成長させる“仕組み”になります。
参考|ファンダムマーケティングと共創マーケティングの関係
「ファンダムマーケティング」という言葉は比較的新しいものですが、その考え方の源流は日本でもすでに存在していました。たとえば「共創マーケティング」や「アンバサダーマーケティング」といった取り組みです。ユーザーの声を商品開発に取り入れたり、熱心なファンをブランドの応援団として迎える活動は、多くの企業で長く行われてきました。
こうした動きとファンダムマーケティングの違いは、ファンの“熱量”を中心に据えているかどうかです。共創やアンバサダーの仕組みはファン参加の枠組みを作ることに重点がありましたが、ファンダムマーケティングはその先で「どう熱を生み出し、維持していくか」に注目しています。
つまりファンダムマーケティングは、従来の手法を“熱量”という視点で再定義したものだといえます。過去の取り組みを振り返りつつ、この観点から整理すると、今の時代におけるマーケティングの可能性が見えてきます。
事例に学ぶファンダムマーケティング
ファンダムマーケティングの具体像をイメージできるように、事例を紹介します。
Klairs(クレアス):韓国発スキンケアブランド
韓国発のスキンケアブランド「Klairs」は、ファンダムを活かした展開で注目を集めています。MUSINSAでの先行発売やプロ野球選手のアンバサダー起用、ビューティーインフルエンサーとのコラボレーションなど、ファンの関心を引き込む取り組みを重ね、コミュニティを通じて話題を広げてきました。
この動きは日本市場にも広がりを見せており、Qoo10でのインフルエンサー施策に加え、2025年5月にはインフルエンサー約250名を集めたオフラインイベントを実施。新作の商品を体験するワークショップは即座に満席となり、ファンの熱量を可視化しました。
クレアスはこうした取り組みを通じて、インフルエンサーを起点にファンダムを形成し、その熱を一般消費者へと広げていく動きを見せています。
ワークマン:ファンを巻き込むアンバサダー制度
作業服ブランドからスタートしたワークマンは、近年アウトドアやカジュアルウェアへと市場を広げています。その背景には、ファンを積極的に巻き込むファンダムマーケティングの仕組みがあります。
同社はアンバサダー制度を導入し、愛用者やインフルエンサーに公式な発信の場を提供しました。ブランドの一員として発信を任せることで、企業の広告以上にリアルな情報が広がり、自然な支持が拡大しています。さらに、SNSで集まる意見を商品開発に反映し、「自分の声が形になった」と感じられる体験を提供。ファンが共創者としてブランドに関わる姿勢が、多くの支持を集めています。
アサヒビール:カルチャーファンダムとの接点づくり
アサヒビールは、スポーツや音楽カルチャーのファンダムの熱量を活用するアプローチを展開しています。期間限定の没入型コンセプトショップやアーティストとのコラボイベントを通じて、カルチャーの既存ファンダムと自社のブランドとの接点を構築し、新たな顧客の創造を目指すさまざまな取り組みが行われています。
ファンダムをキーワードにした企業やブランドの取り組みは着実に広がっており、マーケティングの新しい潮流として目が離せません。
ファンダムマーケティングの取り入れ方
ファンダムマーケティングというと大掛かりな施策を思い浮かべがちですが、実際には小さな工夫から始めることができます。ポイントは、ファンを「消費者」ではなく「関わる仲間」として扱う視点です。
◆声をすくいあげる仕組みをつくる
SNSでのコメント募集やアンケートなど、簡単な方法でも「意見が届く」と実感できる場があれば、ファンは自然と参加意識を高めます。
◆共感を共有する
ユーザー投稿やレビューを公式SNSや店舗で紹介するだけで、「自分もその一員だ」という感覚を広げられます。
◆小さなリアル体験を設ける
座談会やワークショップのように、少人数でも直接ブランドに関われる機会があると、ファンの熱量は一気に高まります。
特別な仕組みは必要なく、日々の活動の延長で取り入れられることばかりです。小さな一歩の積み重ねが、ファンダムを育てる大きな力につながります。
一方で、ファンダム全体に向けたメッセージを届けることも重要です。すでに存在するカルチャーやコミュニティに寄り添い、共感を示すことで、ブランドは「仲間」として受け入れられます。
◆カルチャーやコミュニティとの接点を持つ
音楽やスポーツ、アニメなど熱量の高いファンダムに協賛・コラボし、自然にブランドを重ねる。
◆ファンダムに寄り添った体験を提供する
既存のコミュニティに参加しやすいイベントや商品体験を用意し、ファン同士の盛り上がりに加わる。
◆共感できるストーリーを発信する
商品の機能訴求だけでなく、ファンダムの価値観に響くメッセージを打ち出す。
自社のファンに寄り添う一歩と、広いファンダムに共感を届ける姿勢。その両方を意識することで、ブランドはファンダムと自然につながり、共感を広げていくことができます。
ファンダムを活かしたブランド体験へ
ファンダムマーケティングは、単なるトレンドワードではなく、ファンの熱量を力に変える新しいマーケティングの流れです。小さな工夫から始められるからこそ、多くのブランドが取り入れる可能性を秘めています。
私たちビーツは、展示会や店舗、ポップアップなどリアルな場でのプロモーションを数多く手がけてきました。ファンが集まり、共感を生み、ブランド体験が広がる場づくりこそが私たちの強みです。
オンライン・オフラインを問わず、ファンダムの熱を活かす空間デザインや施策に関心があれば、ぜひご相談ください。リアルな顧客体験を起点に、ファンダムを育てるマーケティングを共に実現していきます。
ファンダムが集まるリアルな場づくりはビーツにおまかせ
ポップアップストアやポップアップイベントはまさにファンが集まり熱量を共有する代表的な場所です。SNSでつながっていたファンがリアルに出会い、ブランドの世界観を体感することで、共感はさらに強まり、発信の力へと変わっていきます。写真を撮りたくなる空間や、共感を生む演出があれば、ファンは自発的に発信し、ブランドの世界観を仲間と共有します。

ビーツは、こうした体験の空間づくりを得意としています。訪れたくなる店舗のデザインや、思わず投稿したくなる工夫を盛り込み、リアル体験とオンラインでの広がりを後押したさまざまな事例はホームページでご覧いただけます。
ファンダムの熱をリアルで高め、その熱をSNSで広げたいときは、ぜひビーツにご相談ください。
▼詳しくはサービスページをご覧ください
▼こちらの記事もおすすめ

▼ポップアップストア&イベントサービス資料は以下よりダウンロードいただけます